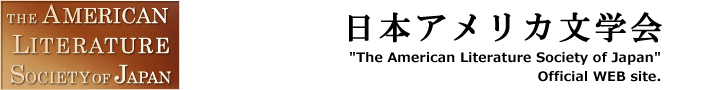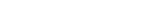- ホーム
- 各支部からのお知らせ
各支部からのお知らせ
東京支部11月例会(オンライン開催)のお知らせ
2021/10/242021年11月13日(土)午後1時30分より
オンライン(Zoom・事前申込制)で開催いたします。
詳細は、10月下旬に支部HPでお知らせいたします。
会員以外の方の参加も歓迎いたします。
研究発表
ウィラ・キャザーと語りの哀悼可能性
講師:山本洋平(明治大学)
司会:新井景子(武蔵大学)
分科会
近代散文:Harriet JacobsのIncidents in the Life of a Slave Girlにおける海の表象
名和玲(東京理科大学・非)
現代散文:花束と物質主義
『教授の家』における絵画の機能
相木裕史(津田塾大学)
詩:ポーの「視線恐怖」の表と裏
“To Helen”を“The Tell-Tale Heart”との比較で読む
宇佐教子(東京都立大学・非)
演劇・表象:演劇とラジオが交わる時
ミュージカルBillion Dollar Baby (1945) の号外場面に着目して
辻佐保子(早稲田大学)
関西支部11月例会のご案内
2021/10/19日本アメリカ文学会関西支部11月例会のご案内
2021年度日本アメリカ文学会関西支部11月例会を下記のとおりオンラインで開催いたします。多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
■日時:2021年11月6日(土)15時より
■Zoomによる開催(参加リンク等は後日メールでお知らせします)
■研究発表
1.「敗北を握りしめて−Don DeLilloのUnderworldにおける自己内省の触媒としての野球」
発表者 中村瑞樹(大阪大学・院)
司会 木原善彦(大阪大学)
2.「Pierreにおける音、音楽とノイズ 」
発表者 真田満(龍谷大学・非)
司会 野田明(三重大学)
3.「エマソンのNatureの曖昧性」
発表者 小田敦子(三重大学)
司会 藤田佳子(奈良女子大学・名)
(18時頃終了予定)
中部支部 9月例会(2021)のお知らせ
2021/09/01以下の要領で中部支部9月例会を開催します。
*日時:9月18日(土)午後2時より*
Zoomによるオンライン会議形式で開催します。
→参加方法は事務局からのメールにてご確認ください。
*発表*
(1) 平沼公子氏(名古屋短期大学) 司会:柳楽有里氏
「1950年代はいかに語れるのかーWalter Mosley の A Red Death における冷戦下の人種共闘」
(2) 宮澤優樹氏(金沢大学) 司会:水口陽子氏
「Edith Wharton の Ethan Frome における曖昧性ーTurner の絵画を出発点に」
【例会終了後、運営委員会を開催します。】
東京支部9月例会(オンライン開催)のお知らせ
2021/08/302021年9月18日(土)午後1時30分より
オンライン(Zoom・事前申込制)で開催いたします。
詳細は、9月4日頃に支部HPでお知らせいたします。
会員以外の方の参加も歓迎いたします。
研究発表
亡霊のソーシャリズム
講師:貞廣真紀(明治学院大学)
司会:千石英世(立教大学名誉教授)
分科会
近代散文:未だ口にされない証言
板垣真任(日本工業大学・非)
現代散文:“This Is Still Good Country”
Ambivalent White Masculinity in Cormac McCarthy’s All the Pretty Horses
Rong Qin(東京工業大学・院)
詩:“To a Locomotive in Winter”を再読する
川崎浩太郎(駒澤大学)
演劇・表象:「有色人種」の構築とそのパラドックス
世紀転換期のアメリカ映画における人種イデオロギーの表象
福西恵子(ハワイ大学・院)九州支部 九州支部9月例会のご案内
2021/08/04九州アメリカ文学会9月例会
日時:2021年9月4日(土) 13時00分から17時00分
場所:Zoom会議
接続先URL、ミーティングID、パスワードは例会前日にKALSのメーリングリストを通じてお知らせします。
[研究発表①] 13時10分から14時10分
発表者:吉村幸
「Intruder in the Dustとアメリカ合衆国の人種主義−真犯人Crawford Gowrieが
暴くFaulknerの南部への執着」
司会: 永尾悟(熊本大学)
[研究発表②] 14時20分から15時20分
発表者:毛利優花(西南学院大学大学院博士後期課程)
「フィリップ・K・ディックの『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』考察
—薬物による幻覚作用、アイデンティティの危機、テクノロジーが持つ共感性を考える—」
司会: 新田よしみ(福岡大学)
[研究発表③] 15時30分から16時30分
発表者:藤原まみ(山口大学)
「Jack Londonと中田由松」
司会:森考晴(鹿児島国際大学)
関西支部7月例会のご案内
2021/06/27関西支部7月例会のご案内
2021年度日本アメリカ文学会関西支部7月例会を下記のとおりオンラインで開催いたします。今回の企画は、ASLE-Japan/文学・環境学会と合同開催のミニシンポジウムとなっております。多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。
■日時:2021年7月10日(土)午後3時より
■Zoomによる開催(参加リンク等は後日メールでお知らせします)
■ミニシンポジウム「非日常性のアメリカ文学」
登壇者(敬称略)
【司会】浜本隆三(甲南大学)
【講師】林千恵子(京都工芸繊維大学)
新関芳生(関西学院大学)
坂根隆広(関西学院大学)
中山悟視(尚絅学院大学)
(講師の先生方の発表タイトルにつきましては、後日Zoomリンクとともにお知らせする予定です。)
東北支部6月例会(ハイブリッド開催)のお知らせ
2021/06/07日時:2021年6月19日(土)15:00〜16:30
会場:ハイブリッド開催とします、詳細は以下のとおりです。
研究発表
清水菜穂(宮城学院女子大学)
「Adrienne Kennedyの「劇中劇」の手法—The Alexander Plays の4作品をめぐって(仮)」
扱う作家: Kennedy, Adrienne.
作品: The Alexander Plays. University of Minnesota Press,1992.
なお、研究発表は司会なし、事務局の進行で行ないます。
東京支部6月例会(オンライン開催)のお知らせ
2021/06/072021年6月26日(土)午後1時30分より
オンライン(Zoom・事前申込制)で開催いたします。
詳細は、6月中旬頃に支部HPでお知らせいたします。
会員以外の方の参加も歓迎いたします。
シンポジウム
戯曲研究と翻訳上演
司会:佐藤里野(東洋大学)
講師:小田島恒志(早稲田大学)
講師:黒田絵美子(中央大学)
講師:相原直美(千葉工業大学)
分科会
近代散文:“Life Without Principle”におけるThoreauの社会批判と死生観との関係性をめぐって
西田梨紗(大正大学・院・単位取得満期退学)
現代散文:「東」への帰還
「キリマンジャロの雪」における死のイメージ
詩:MelvilleとGlobal South
‟At the Hostelry” を中心に
佐久間みかよ(学習院女子大学)
演劇・表象:『ハミルトン』
ブロードウェイでよみがえる異端の建国の父
谷佐保子(早稲田大学・非)
詳細は支部HPをご覧ください。
日本アメリカ文学会中部支部 6月例会(2021)のお知らせ
2021/06/06*日時:6月19日(土)午後2時より*
Zoomによるオンライン会議形式で開催します。 →参加方法は事務局からのメールにてご確認下さい。
*発表*
(1) 梶原克教氏(愛知県立大学) 司会:平沼公子氏
「ハーレム・ルネサンスにおける身体の位置」
(2) 山本伸氏(東海学園大学) 司会:杉浦清文氏
「突き抜ける母性と生と死の融合—エドウィージ・ダンティカの世界」
*「読書会」指定テクスト募集
例年 12 月に開催される「読書会」(ワークショップ)で扱う、
指定テクストを募集致しています。ご推薦頂ける場合は、
6 月 19 日までに竹野先生(ftakeno5@gmail.com)まで連絡ください。
対象作品のジャンルは問いません。
【例会終了後、運営委員会を開催します。】
中・四国支部 第49回大会(オンライン開催)のご案内
2021/05/29日時:6月12日(土) 10:30〜18:30
【プログラム】
開会の辞 (10:30〜10:40)
会長: 前田 一平 (鳴門教育大学)
研究発表 (10:40〜14:10)
司会: 松永 京子 (広島大学)
1. 10:40〜11:20
「語りかける世界 Li-Young LeeのBehind My Eyesにおける対話の機能」
発表者: 風早 由佳 (岡山県立大学)
2. 11:20〜12:00
「Nina Revoyr作品における「水」表象」
発表者: 渡邊 真理香 (北九州市立大学)
司会: 吉田 美津 (松山大学名誉教授)
3. 12:50〜13:30
「日系アメリカ人二世作家の描く母と娘の物語
—— “Seventeen Syllables”と“And the Soul Shall Dance”における母娘」
発表者: 遠藤 緑 (鳥取短期大学)
4. 13:30〜14:10
「国立公園都市計画のハイブリディティ構造 —— John Muirの自然論から現代生活を考える」
発表者: 真野 剛 (海上保安大学校)
特別講演 (14:20〜15:20)
司会: 前田 一平 (鳴門教育大学)
講師: 上西 哲雄 氏 (東京工業大学名誉教授)
演題: 「キリスト教とアメリカ文学」
シンポジアム (15:30〜18:00)
『21世紀から読み直すアメリカ自然主義文学』
司会: 増崎 恒 (追手門学院大学)
1. 「Stephen Crane、ニューヨーク市、外国(人・語)、国際感覚
—— アメリカ自然主義文学における「環境」の力を再考する」
発題: 増崎 恒
2. 「The Octopusにおける超自然的“FORCE” —— 人新世の文学としてのアメリカ自然主義文学」
発題: 菅井 大地 (松山大学)
3. 「London自身の自然主義 —— その現代社会における意味」
発題: 劉 鵬 (遼寧対外経貿学院(中国))
4. 「Jack Londonが現代に示唆するもの」
発題: 森 孝晴 (鹿児島国際大学)
総会 (18:00〜18:20)
議長(会長): 前田 一平
閉会の辞 (18:20〜18:30)
副会長: 大地 真介 (広島大学)