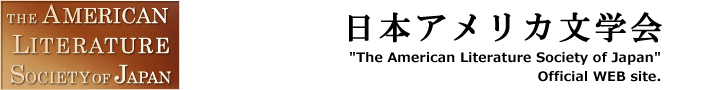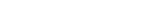- ホーム
- 各支部からのお知らせ
- 北海道支部
各支部からのお知らせ
北海道支部第159回研究談話会のご案内
2012/04/24第159回研究談話会を下記の要領にて開催いたします。どうぞお誘いあわせの上、多数お集まり下さいます様ご案内申し上げます。なお今回は北海道大学英文学会との共催です。
◆日時:4月28日(土)午後4時 〜 5時30分
◆場所:北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟 W409
札幌市北区北10条西7丁目 正門より徒歩7分、総合博物館向かい
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~k15696/home/Map.doc
▼題 目: “Nakeder than Adam and Eve”: Theodicy, Empire, and “Systemless System” in the New Edition of the Autobiography of Mark Twain
▼発表者:Mr. Harold K. Bush, Jr., Saint Louis University
▼司 会:久保 拓也氏(金沢大学)
北海道支部第158回研究談話会のご案内
2012/03/27第158回研究談話会を下記の要領にて開催いたします。また談話会終了後に総会を開催しますので、どうぞお誘いあわせの上、多数お集まり下さいます様ご案内申し上げます。
◆日時:3月31日(土)午後4時〜6時
◆場所:藤女子大学(札幌市北区北16条西2丁目)新館5階 558室
*交通案内:地下鉄南北線「北18条前」下車、徒歩5分
▼題 目:ネイティヴ・スピーカーは誰なのか——Chang-rae Lee, Native Speakerにおける英語イデオロギー
▼発表者:伊藤 章氏(北星学園大学)
▼司 会:皆川 治恵氏(北海道教育大学札幌校)
▼趣旨:
韓国系アメリカ人、Chang-rae Leeの処女作、Native Speaker (1995) は出版されるや評判になり、ヘミングウェイ協会賞など多数の賞を授与された。じつに多様な解釈が可能なテキストであるが、ここでは移民と言語の関係に焦点をあてたい。家庭で韓国語を使っていた語り手は、いかにして英語をマスターしていったのか。韓国語から英語への移行はどのようなものであったのか。英語を学ぶということはどういうことなのか。アジア系でも、ネイティヴ・スピーカーになれるのか。英語が流暢でなければ、アメリカ市民として正式に認知されないのか。そもそもネイティヴ・スピーカーとは誰なのか。そういった問題を問いかけたテキストとして読み解くことにしよう。そこから、アメリカにおいて英語という言語に特別な意味と価値を付与する、英語イデオロギーというべきものが、多文化主義の現代においても移民を支配していることを明らかにしたい。
北海道支部第156回研究談話会のご案内
2011/12/28第156回研究談話会を下記の要領にて開催いたします。どうぞお誘いあわせの上、多数お集まり下さいます様ご案内申し上げます。
◆日時:1月21日(土)午後4時〜6時
◆場所:藤女子大学(札幌市北区北16条西2丁目)新館5階 558室
*交通案内:地下鉄南北線「北18条前」下車、徒歩5分
▼題 目:「私は流れるものすべてを愛する」
——ヘンリー・ミラー『北回帰線』における流れの場としての身体と都市
▼発表者:井出 達郎氏(北海道大学大学院)
▼司 会:上西 哲雄氏(東京工業大学)
▼趣旨:
『南回帰線』のエピグラフ「卵巣の市電に乗って」に典型的にみるように、ヘンリー・ミラーの一般的なイメージは、身体性を猥褻的に強調する作家というものだろう。しかし、この標準的な見方は、ミラーに真に特徴的なものを見落としてしまう。このエピグラフで真に特徴的なもの、それは、卵巣という身体の一器官(organ)が、市電という都市の一機関(organ)と結びつけられている点である。この点に注目して彼の作品群を読むと、身体を都市のように描く場面、また都市を身体のように描く場面が多いことに気づく。では、なぜミラーは身体と都市を結びつけて描くのか。
今発表は、ミラーの実質的な処女作である『北回帰線』(1934年)を取りあげ、ミラーにおける身体と都市の結びつきの問題に対して、彼が二つの場所を同じ流れの場として描こうとしている、という解釈を提示する。もともと身体と都市は、近代以降、隅々にまで名称=住所が割り振られ、秩序のもとに編成されること(organization)によって、権力が強力に働きかける場所として今なおあり続けている。ミラーのテクストから立ち上がってくるのは、そうした名称=住所の秩序化による区分線を解体し、固定的に分節化された場所を流動化させようとする衝動である。その流れの場に、あたかも細胞分裂を始める卵(らん)のように、さまざまなものに生成する可能性を見出して力強く肯定すること、ミラーの最初の作品である『北回帰線』は、後続の作品群を貫く身体と都市の問題に、そうした衝動を胚胎させたテクストとしてある。
北海道支部第155回研究談話会のご案内
2011/11/14第155回研究談話会を下記の要領にて開催いたします。どうぞお誘いあわせの上、多数お集まり下さいます様ご案内申し上げます。
◆日時:11月26日(土)午後4時〜6時
◆場所:北海学園大学(札幌市豊平区旭町4丁目1番40号)7号館1階 演習室D101
*交通案内:地下鉄東豊線「学園前」駅で降りて3番出口をご利用下さい。
7号館は、地下鉄の上にある6号館から正門をはさんで反対側、平岸通(平岸街道)沿いにあります。
▼題 目:「白い血」という檻──Go Down, MosesにおけるIkeの人種的思考
▼発表者:本村 浩二氏(関東学院大学)
▼司 会:平野 温美氏
▼要 旨:
William FaulknerのGo Down, Moses (1942)第六章の“Delta Autumn”の終盤に、Issac [Ike] McCaslinがアメリカ社会で顕在化しつつある、異人種間の混淆と混血について、悲嘆の意を表明する、有名な場面がある。南部の貴族階級出身で、今や老人(73歳)となっている彼がそこで恐れているのは、人種的差異の喪失がもたらす混乱と無秩序である。そしてその喪失は、この老人の独自のロジックによれば、理不尽な森林破壊が引き金となって生じている。
改めて言うまでもなく、彼の、人種的差異の希求の背後には、人種の“purity”の保持という欲望がある。確かに、批評家Thadious M. Davisが指摘しているように、彼の、世襲財産と所有権の放棄は、当時アメリカ全土で広く受け入れられていた“scientific racism”に逆らう行為となっている。しかしながら、そのポジティヴな意味が、“Delta Autumn”の終盤の場面における心境の表白によって、大いに否定されているのも事実である。
さて、本発表は、Ikeを主人公にしている、いわゆる“the wilderness trilogy”── “The Old People”、“The Bear”、“Delta Autumn”──を主に取り上げるが、それらを従来の研究によく見られた型、つまり、主人公が荒野での神秘的なエピファニー体験に基づき、己の家系の罪深い暗部に開眼していくという、ビルドゥングスロマン(社会的、道徳的、精神的成長の物語)として読むのではない。というのも、彼の長い人生の物語には、厳密な意味で「成長」という二文字がうまく当てはまらないように思われるからだ。
この時代の人種イデオロギーに光を当てつつ、むしろ本発表で試みたいのは、“purity”と”hybridity”をキーワードに使いながら、Ikeの生涯を彼自身の身体に流れているとされる「白い血」との闘争の物語として読むことである。もう少し具体的に言うなら、それは、彼が祖父から受け継いた「白い血」の呪縛にとらわれ、如何に自由になれずに、苦悩しているのかを確認することである。
こうした視点からの読みは、「白人」という人種カテゴリーの標準・規範を問うという意味で、近年盛んなホワイトネス研究が提起している問題を多少なりとも共有することになるであろう。