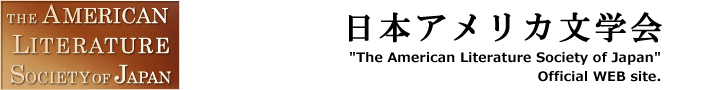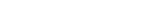- ホーム
- 全国大会
- 第51回 全国大会
- <第1日> 10月13日(土)
- 第1室(全学教育棟本館S10講義室)
- 1.Dr. Templetonのヒル——“A Tale of the Ragged Mountains”とメスメリズム
1.Dr. Templetonのヒル——“A Tale of the Ragged Mountains”とメスメリズム
宮澤 直美 京都産業大学
Edgar Allan Poeの作品には骨相学を始め様々な擬似科学が登場してくる。なかでも、“A Tale of the Ragged Mountains” (1844)、 “Mesmeric Revelation” (1844)、“The Facts in the Case of M. Valdemar” (1845)といった作品は、当時流行していたメスメリズム、あるいは動物磁気学を強く意識した作品である。18世紀後半のパリで、Franz Anton Mesmer (1733-1815) によって提唱されたメスメリズムは、メスメリストと患者との間に“rapport”を形成し、睡眠状態になった患者に“vital fluids”を送り込むことで、病気を治すというものだ。フロイト心理学にも通じるこの擬似科学は、病気を治すだけでなく、人の心の中に入り込み精神的交流を可能にすると信じられていた。
本発表では、“A Tale of the Ragged Mountains”を中心に、Poeの編み出すメスメリックな作品世界と創作論を再検証したいと思う。患者であるBedloeとの間に特殊な信頼関係を築いたDoctor Templetonは、クライマックスで、毒素のあるヒルを医学用のヒルと取り間違え、Bedloeに処方し死に至らしめる。Bedloeの死によって過去の人物であるOldebとBedloeの奇妙な一致はより完成されたものへと近づくのだが、これを全く悪意のない医療ミスと解釈するかどうかは読者に委ねられているように思う。Doctor Templetonに殺意はなかったのだろうか。ピューリタン的言説が、ヒルや蛇を悪魔の象徴と考えてきた伝統に鑑みると、ヒルはDoctor Templetonの心の中に誘惑として忍び寄り、彼を殺人鬼へと誘った黒い影だと解釈することも可能だ。解釈の可能性の中に読者を取り残すことこそが、読者をメスメライズするためにPoeが仕組んだ効果なのかもしれない。
1827年のCharlottesvilleという具体的な場面設定をしたり、擬似科学を用いたり植字ミスを導入したりと本作品は一見、Poeの美女再生譚にみられるようなロマン主義から距離を置き、超現実的な出来事をいかにリアルに本物らしく描き出すかを狙っているようにも思える。しかし、ヒルに象徴されるDoctor Templetonの心に潜む影と、不合理なまでに重なり合う「偶然」の数々は、超現実的な世界を不気味に照らし出す。このような作品世界を作り出すのに、メスメリズムがどのような役割を担っているのか、また、Poeがどのような効果を狙って作品に登場させているのか考察したいと思う。
Nathaniel Hawthorneについての書評に、“Review on Nathaniel Hawthorne's Twice-Told Tales”(1842)がある。このなかで、“single sitting”で読み切れる作品の短さが読者を作品世界に取り込むためには重要であると主張したPoeの創作論からは、読書体験を通じて、読者を“control”し、メスメリズム的な効果を読者に与えることを、ひとつのもくろみにしている様子が伺える。本発表では、“A Tale of the Ragged Mountains”から出発し、Poeの創作論とメスメリズムとの関係性についても考察したいと思う。